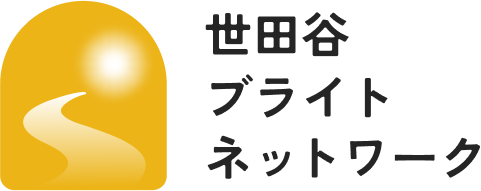「不登校当事者による多様な進路交流会」レポート⑥ 〜学校の先生の思い〜
2025年3月20日(祝)、三軒茶屋のキャロットタワー5階にて「不登校当事者による多様な進路交流会」が行われ、子ども、保護者、不登校経験のある子どもを支える学校の先生から経験談が語られました。この記事では、不登校経験のある子どもを支えたご経験をお持ちの学校の先生のお話をまとめています。
世田谷区のチャレンジスクールである世田谷泉高校で教鞭を取られており、ご自身も不登校経験を経験された渡邊智寛先生と、小学校と定時制高校で養護教諭を務められ、現在は千葉大学で研究と後進の育成にあたられている沖津奈緒先生が、ご自身のご経験と思いをお話しくださりました。
〜こちらもあわせてお読みください〜
★過去の「不登校当事者による多様な進路交流会」会場レポートはこちら
みなさん、こんにちは。新卒2年目で世田谷泉高校の教員をしております、渡邊と申します。今は1年生を担当しておりまして、去年は4〜6年生の担当でした。
私も不登校経験をしています。小学校時代には野球チームでキャプテンを務めていて、チーム内でいざこざがあり、小4で1回学校に行かなくなりました。その後なんとか頑張って登校したんですけれども、チームメイトの人と同じ中学校の野球部に所属して当時のことを言われ、最初はいじりだったものが、だんだんいじめのような形に変わっていきました。もう学校っていうものが嫌で嫌でしょうがなかった。先生という存在も本当に嫌いでした。そこから、家にずっと閉じこもって、親とはずっと喧嘩をして、泣きわめき…という1年間を過ごしました。
そんな中、私の住んでいた自治体の不登校生徒が集まる相談学級で、ある先生から「今のままでいいんだよ。自分のことをこのまま認めてあげて。」と言われたことで、自分は本当に救われたと思っています。両親の助けもあり、区内の中学校に転校することができました。
中学校の不登校時代に通っていたクリニックで見かけた高校生が「輝いてるな」と思ったのですが、その高校は偏差値が高く、内申点も必要でした。これは無理だなって思ってたんですけれども、憧れのその高校に行きたいと思って頑張って受験勉強をして、合格しました。そこで環境が変わって、のびのびと過ごすことができました。
私が今教員としてこの場に立って話ができているのは、環境のおかげだと思っています。先生との出会いもそうですし、両親の頑張りもそうですし、その後の友人関係にも恵まれたと思います。今度は私自身が、何気ない一言で考え方を変えてあげられるような存在、支えてあげられるような存在になりたいと思って、今教員をやっています。
今不登校で苦しんでいるとか、学校に行けなくて、なかなか苦しんでいる人がいると思うんですけれども、「今を生きている」それだけで僕は十分だと思っています。そして、保護者の方々は相当つらいですよね。一生懸命良かれと思ってやっても、返ってくる言葉は「クソババア、クソジジイ」で、そっけない態度。私自身も両親によくやっていました。そうやって反発していても、裏では「ごめんね」って思っていたんです。そして、今は「ありがとう」と感謝をしたい気持ちでいっぱいです。なので、今その子が生きられるのは、保護者の方々のおかげだと思っています。
世田谷泉の生徒は本当に優しいと思います。なにより、相手を思って行動ができます。生徒にとって久しぶりの学校ですから、友人関係でのトラブルはいろいろあるんですけれども、その中で試行錯誤しながら、日々今を一生懸命生きている生徒が沢山います。その生徒たちには「1年間よく頑張ったね。1年前はこんな姿を想像できなかったよね。今を生きたから実現できたんだよ。これからも一緒に頑張っていきましょう。」というようなことを伝えています。
大人にできることは環境づくりだと思います。それぞれの生徒が大きな花を咲かせる種を持っていて、その花を咲かせられる環境をつくるのは我々大人の役割です。まだ微力ですが、私も、安心して学校に登校できる、「世田谷泉に来てよかったな」「今日も学校に出てよかったな」と思ってもらえる環境づくりをするために、日々生徒と向き合っています。
私も不登校経験をしています。小学校時代には野球チームでキャプテンを務めていて、チーム内でいざこざがあり、小4で1回学校に行かなくなりました。その後なんとか頑張って登校したんですけれども、チームメイトの人と同じ中学校の野球部に所属して当時のことを言われ、最初はいじりだったものが、だんだんいじめのような形に変わっていきました。もう学校っていうものが嫌で嫌でしょうがなかった。先生という存在も本当に嫌いでした。そこから、家にずっと閉じこもって、親とはずっと喧嘩をして、泣きわめき…という1年間を過ごしました。
そんな中、私の住んでいた自治体の不登校生徒が集まる相談学級で、ある先生から「今のままでいいんだよ。自分のことをこのまま認めてあげて。」と言われたことで、自分は本当に救われたと思っています。両親の助けもあり、区内の中学校に転校することができました。
中学校の不登校時代に通っていたクリニックで見かけた高校生が「輝いてるな」と思ったのですが、その高校は偏差値が高く、内申点も必要でした。これは無理だなって思ってたんですけれども、憧れのその高校に行きたいと思って頑張って受験勉強をして、合格しました。そこで環境が変わって、のびのびと過ごすことができました。
私が今教員としてこの場に立って話ができているのは、環境のおかげだと思っています。先生との出会いもそうですし、両親の頑張りもそうですし、その後の友人関係にも恵まれたと思います。今度は私自身が、何気ない一言で考え方を変えてあげられるような存在、支えてあげられるような存在になりたいと思って、今教員をやっています。
今不登校で苦しんでいるとか、学校に行けなくて、なかなか苦しんでいる人がいると思うんですけれども、「今を生きている」それだけで僕は十分だと思っています。そして、保護者の方々は相当つらいですよね。一生懸命良かれと思ってやっても、返ってくる言葉は「クソババア、クソジジイ」で、そっけない態度。私自身も両親によくやっていました。そうやって反発していても、裏では「ごめんね」って思っていたんです。そして、今は「ありがとう」と感謝をしたい気持ちでいっぱいです。なので、今その子が生きられるのは、保護者の方々のおかげだと思っています。
世田谷泉の生徒は本当に優しいと思います。なにより、相手を思って行動ができます。生徒にとって久しぶりの学校ですから、友人関係でのトラブルはいろいろあるんですけれども、その中で試行錯誤しながら、日々今を一生懸命生きている生徒が沢山います。その生徒たちには「1年間よく頑張ったね。1年前はこんな姿を想像できなかったよね。今を生きたから実現できたんだよ。これからも一緒に頑張っていきましょう。」というようなことを伝えています。
大人にできることは環境づくりだと思います。それぞれの生徒が大きな花を咲かせる種を持っていて、その花を咲かせられる環境をつくるのは我々大人の役割です。まだ微力ですが、私も、安心して学校に登校できる、「世田谷泉に来てよかったな」「今日も学校に出てよかったな」と思ってもらえる環境づくりをするために、日々生徒と向き合っています。
私は6年間、福島県の小学校と定時制高校で、養護教諭、いわゆる保健室の先生の仕事をしていました。今はそちらを辞めて、大学で養護教諭を養成する仕事に就いています。今日は、養護教諭としてどのように不登校のお子さんや保護者に関わってきたかをお話しさせていただきます。
小学校に勤めていた時には、保健室登校とか不登校だった子どもが、私が着任したときにはゼロでした。今では小学校で保健室登校という4割ぐらいの学校が全国的にはいると言われている中で、少しかえって変わった学校だったのかなと思ったりしています。着任して3年目くらいのときに、登校しぶりだった女の子が現れまして、私自身も保健室登校とか登校しぶりということが初めてだったので、その子に対してはうまく支援ができなかったなと。一言で言うと、私の中での失敗体験になっています。最後までその子は前進している様子はなく、その子との別れになってしまいました。
次に定時制高校に着任しました。初めは「やってやるぞ、何か力になるぞ」と張り切っていたのですが、「私が頑張るぞ」というのは何か違うなと感じるようになりました。定時制高校の中で気づいた、私なりの支援の形について、3つお話ししたいと思います。
1つめは、子ども同士の交流の機会をつくることの大切さです。私が着任したときには、保健室に来た子どもたちをどうケアするかと、保健室の中でできることを考えていたんですけれども、定時制高校の子どもたちを見ていたら、保健室をたまに休む場所として、あるいは少し話をしたくて来るといったように、うまく使っているという印象でした。また、子どもの様子を知るために行事や授業の様子を見てみると、子どもたち同士の交流のなかで自己開示をしていたり相手を理解したりし、子どもたちなりに少しずつ学校に居場所を作っていることに気づきました。子ども同士の交流の場とか機会、そういうようなものをいかにして作るかが、支援として大事ということを子どもたちから教わったように思います。私が保健室に来る子どもからの要求に何とか応えたいとのめり込みそうになった時に、違う生徒が私にアドバイスしてくるんです。「先生、それは時間がすごくかかるから、こうした方がいいよ」「先生、その場所じゃなくて、あっちの部屋のほうが話しやすそうだよ」とアドバイスをくれることもありました。多分同じような経験をしてきたからこそのアドバイスだと思います。
2つめは、1人の人間としての関わりの大切さです。もう1人の養護の先生がよくやっていたのが、子どもが好きな漫画やアニメを一緒に見ることでした。私の母親と同じ年代の養護の先生でしたけど、漫画のセリフを生徒と言い合ったりとかして、子どもとの共通の趣味を味わっているようでした。それが教育かというと少し違うのかもしれません。しかし、その様子から、大人と子どもという関係というよりは、1人の人として何かを一緒に楽しむ時間や関わりが、子どもたちを癒していることに気づきました。
3つめは、保護者を支えることの大切さです。これも生徒から気づかせてもらいました。家庭のことも話を聞いたりするんですけれども、「お母さんとかお父さんに言いたいけれども、やっぱり言いにくい。でもそれは大事だからこそ言いにくい。」とか、「うちのお母さん、今こんな勉強をしていて、めちゃくちゃかっこいいんだ」という話をしたりするんですね。また、実際に学校に来れていないお子さんには直接支援ができないので、その代わりにお母さんとか保護者の方と話をする機会が結構ありましたけれども、お母さん自身がやはりお子さんと一緒に具合が悪くなっていたりとか、落ち込まれていたりとか、とにかく孤立しているという状況をすごく感じました。お子さんの様子とかお母さん方との話の中で、その子への登校をめぐる支援だけではなくて、子どもの家族、お母さんやお父さんを支えるということを、学校はあまりやっていないんじゃないか。そういう支援はすごく足りていないと感じました。そのときの問題意識から、今は保護者支援につながるような調査研究もしてきました。
あと、支援とは関係ないんですけれども、生徒さんに気づかされたことで、私にとって大事なことがあるので、お伝えしたいなと思います。学校の先生たちは、今関わっている子どもたちの卒業後の姿を見ることがなかなかできないと思います。私が関わった定時制高校の子どもたちは保健室に対する信頼感が大きくて、「保健室のおかげで今の自分がある」「保健の先生との関わりはすごく自分にとって良かった、成長になった」と話してくれることがあったんですね。これは、悩みながらも子どもたちを支えている養護の先生たちがなかなか知ることのない子どもの声だと思うので、こういうことを養護の先生たちにできるだけたくさん伝えるようにしています。
また、私は不登校の子を持つ保護者の方へのアンケート調査をさせていただきました。成果はまだまとめきれていないのですが、調査結果の一部をご紹介します。
「保護者が子どもの不登校を経てどう変化したのか」という点に関心があり、調査を行いました。そのなかで、子どもとより心地良い関係を築けるようになるまでの保護者自身の変化の促進要因として「同じ経験をした方との交流」が明らかになりました。なので、保護者の方同士の交流の機会が、自身の経験を意味付けて成長していくことに影響があると言えそうです。
小学校に勤めていた時には、保健室登校とか不登校だった子どもが、私が着任したときにはゼロでした。今では小学校で保健室登校という4割ぐらいの学校が全国的にはいると言われている中で、少しかえって変わった学校だったのかなと思ったりしています。着任して3年目くらいのときに、登校しぶりだった女の子が現れまして、私自身も保健室登校とか登校しぶりということが初めてだったので、その子に対してはうまく支援ができなかったなと。一言で言うと、私の中での失敗体験になっています。最後までその子は前進している様子はなく、その子との別れになってしまいました。
次に定時制高校に着任しました。初めは「やってやるぞ、何か力になるぞ」と張り切っていたのですが、「私が頑張るぞ」というのは何か違うなと感じるようになりました。定時制高校の中で気づいた、私なりの支援の形について、3つお話ししたいと思います。
1つめは、子ども同士の交流の機会をつくることの大切さです。私が着任したときには、保健室に来た子どもたちをどうケアするかと、保健室の中でできることを考えていたんですけれども、定時制高校の子どもたちを見ていたら、保健室をたまに休む場所として、あるいは少し話をしたくて来るといったように、うまく使っているという印象でした。また、子どもの様子を知るために行事や授業の様子を見てみると、子どもたち同士の交流のなかで自己開示をしていたり相手を理解したりし、子どもたちなりに少しずつ学校に居場所を作っていることに気づきました。子ども同士の交流の場とか機会、そういうようなものをいかにして作るかが、支援として大事ということを子どもたちから教わったように思います。私が保健室に来る子どもからの要求に何とか応えたいとのめり込みそうになった時に、違う生徒が私にアドバイスしてくるんです。「先生、それは時間がすごくかかるから、こうした方がいいよ」「先生、その場所じゃなくて、あっちの部屋のほうが話しやすそうだよ」とアドバイスをくれることもありました。多分同じような経験をしてきたからこそのアドバイスだと思います。
2つめは、1人の人間としての関わりの大切さです。もう1人の養護の先生がよくやっていたのが、子どもが好きな漫画やアニメを一緒に見ることでした。私の母親と同じ年代の養護の先生でしたけど、漫画のセリフを生徒と言い合ったりとかして、子どもとの共通の趣味を味わっているようでした。それが教育かというと少し違うのかもしれません。しかし、その様子から、大人と子どもという関係というよりは、1人の人として何かを一緒に楽しむ時間や関わりが、子どもたちを癒していることに気づきました。
3つめは、保護者を支えることの大切さです。これも生徒から気づかせてもらいました。家庭のことも話を聞いたりするんですけれども、「お母さんとかお父さんに言いたいけれども、やっぱり言いにくい。でもそれは大事だからこそ言いにくい。」とか、「うちのお母さん、今こんな勉強をしていて、めちゃくちゃかっこいいんだ」という話をしたりするんですね。また、実際に学校に来れていないお子さんには直接支援ができないので、その代わりにお母さんとか保護者の方と話をする機会が結構ありましたけれども、お母さん自身がやはりお子さんと一緒に具合が悪くなっていたりとか、落ち込まれていたりとか、とにかく孤立しているという状況をすごく感じました。お子さんの様子とかお母さん方との話の中で、その子への登校をめぐる支援だけではなくて、子どもの家族、お母さんやお父さんを支えるということを、学校はあまりやっていないんじゃないか。そういう支援はすごく足りていないと感じました。そのときの問題意識から、今は保護者支援につながるような調査研究もしてきました。
あと、支援とは関係ないんですけれども、生徒さんに気づかされたことで、私にとって大事なことがあるので、お伝えしたいなと思います。学校の先生たちは、今関わっている子どもたちの卒業後の姿を見ることがなかなかできないと思います。私が関わった定時制高校の子どもたちは保健室に対する信頼感が大きくて、「保健室のおかげで今の自分がある」「保健の先生との関わりはすごく自分にとって良かった、成長になった」と話してくれることがあったんですね。これは、悩みながらも子どもたちを支えている養護の先生たちがなかなか知ることのない子どもの声だと思うので、こういうことを養護の先生たちにできるだけたくさん伝えるようにしています。
また、私は不登校の子を持つ保護者の方へのアンケート調査をさせていただきました。成果はまだまとめきれていないのですが、調査結果の一部をご紹介します。
「保護者が子どもの不登校を経てどう変化したのか」という点に関心があり、調査を行いました。そのなかで、子どもとより心地良い関係を築けるようになるまでの保護者自身の変化の促進要因として「同じ経験をした方との交流」が明らかになりました。なので、保護者の方同士の交流の機会が、自身の経験を意味付けて成長していくことに影響があると言えそうです。
いかがだったでしょうか。不登校のお子さんとの関わりについて、学校の先生の視点でのお考えを伺うことができました。本サイトでは学校との関わり方についての記事も掲載しておりますので、学校の先生とお話しをされる際の参考にしていただければと思います。
3月20日の進路交流会で語られた体験談を、6本の記事にわたってご紹介してまいりました。今後も本サイトでは、子ども・保護者向けのイベントや子どものための居場所の現場の様子や、当事者の方々の生の声をコラムとして掲載していきます。ぜひご覧ください!