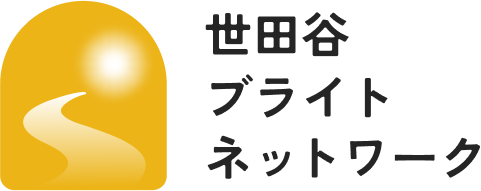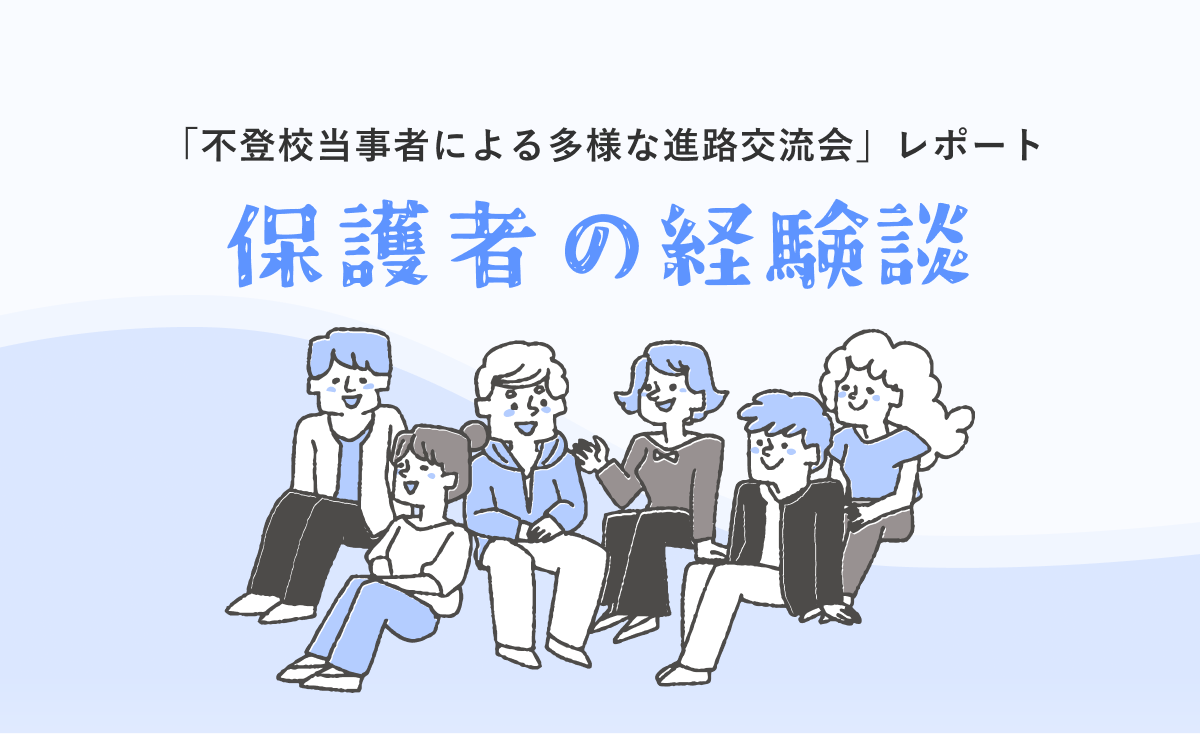
「不登校当事者による多様な進路交流会」レポート④ 〜保護者の経験談 vol.1〜
この記事では、2024年11月4日(祝)に三軒茶屋しゃれなあどホールにて行われた「不登校当事者による多様な進路交流会」の第2部でお話をしてくれた保護者の皆さんの経験談について、まとめています。
保護者の皆さんには、不登校当時のお子さんの様子や現在の様子、その時に保護者として意識していたことや考えたこと、どのような対応をしたのか、を中心にお話を聞きました。また、その経験を経て、同じように悩む保護者の方へのメッセージなどもいただきました。
vol.1の今回は、3名の方のお話を掲載します。
〜こちらもあわせてお読みください〜
通信制高校3年生の息子がいます。高1、2年生の時はeスポーツコースで週2通学で、高3は通信制のみです。中学時代は不登校でした。我が家のキーワードは、「ゲーム」「音楽」「居場所」「役割」です。「音楽」は今回割愛します。ゲームにはまって居場所を失い、学校や地域の友達、部活の仲間を失いました。しかし、ゲームによって新しい居場所や役割を見つけました。オンラインでのコミュニティや、チームでの自分の役割を持つようになりました。
転換点は2つありました。1つ目は、学校に行かせようとすることを諦めたことです。当時私は、決まったことやできないことをやらせようとしていました。でも息子からしたらできないことを「やれ」と言われている状態で、お互いに、精神的にも対応的にも行き詰まってしまいました。
そこで、その時に2つだけ大事なことを決めました。①「親子関係をこれ以上悪くしたくない」ということ。②「生きることを諦めてほしくない」ということ、の2つです。そうなると、学校に行かせようということ自体を諦めざるを得なくなりました。でも結果的には「それが良かった」と後になって息子が言っていました。
転換点の2つ目はゲーミングPCを買い与えたことです。先が見えない中でも、ゲーム自体は強くなりたいという思いがあったので、ゲーミングPCを与え、公式の競技大会に出ました。彼はそこでプロのチームと契約をし、自分の居場所と役割を得ました。高校でも、eスポーツの全国大会に出て、そこでリアルの友達とも繋がることができました。
高校を選ぶときには、最低限の条件を3つ決めました。1つ目は外に出ること、週1でもいいから通えるところであること。2つ目はリアルな友達をつくること。3つ目は高卒資格を取ること。これに関しては現在ほぼなし得たなと思っています。
最近驚いたことは、本人が「この高校に行って良かった」と言っていたことです。通信制に関してとてもコンプレックスを持っていて、それを人に言えなかった彼が「良かった」と言えたところは、とても成長だなと思い、視野が広がったと感じました。さらに、通信制中等部にあるゲーム塾でゲームの講師のアルバイトをしているのですが、その中で「人に教える」ということに興味を持ちました。不登校や特性を持った子たちが、ゲームであればオンラインではなくオフラインでも校舎に集まってくる、ということがあり、eスポーツの教育的効果を感じ、人に教える仕事って面白いな、もっと学びたいと思っているようです。そこから、大学に行きたいというビジョンが見えました。
彼は、”eスポーツ”によって学校に行けなくなり、全てを失いました。しかし、”eスポーツ”によって将来のビジョンが見えてきている、という経緯がとても面白いなと思ってます。彼は大学に行くにはまだ学力が足りませんが、今回AO総合選抜型の入試に挑戦しました。惜しくも2次面接はだめでしたが、1次では自分の不登校についてを小論文で書いていました。不登校であっても、それが子どもたちの人生の足枷にならないような社会をつくるということをテーマにしていました。自分を振り返って、eスポーツをきっかけにオンラインでの居場所から始まり、オフラインでの居場所やそこでの役割を持つことができたこと、それを今後の教育プログラムに組み込めないか、というところまで提起していました。それは、この不登校の経験がなければ考えられなかったことだなと思います。
私自身も、当時から同じ環境の人たちと繋がれたことはとても大きな支えとなっています。今後私自身も、不登校の子の親だったからこそ、こんな面白い経験、体験ができたんだという風に言えるようになりたいなと思っています。
転換点は2つありました。1つ目は、学校に行かせようとすることを諦めたことです。当時私は、決まったことやできないことをやらせようとしていました。でも息子からしたらできないことを「やれ」と言われている状態で、お互いに、精神的にも対応的にも行き詰まってしまいました。
そこで、その時に2つだけ大事なことを決めました。①「親子関係をこれ以上悪くしたくない」ということ。②「生きることを諦めてほしくない」ということ、の2つです。そうなると、学校に行かせようということ自体を諦めざるを得なくなりました。でも結果的には「それが良かった」と後になって息子が言っていました。
転換点の2つ目はゲーミングPCを買い与えたことです。先が見えない中でも、ゲーム自体は強くなりたいという思いがあったので、ゲーミングPCを与え、公式の競技大会に出ました。彼はそこでプロのチームと契約をし、自分の居場所と役割を得ました。高校でも、eスポーツの全国大会に出て、そこでリアルの友達とも繋がることができました。
高校を選ぶときには、最低限の条件を3つ決めました。1つ目は外に出ること、週1でもいいから通えるところであること。2つ目はリアルな友達をつくること。3つ目は高卒資格を取ること。これに関しては現在ほぼなし得たなと思っています。
最近驚いたことは、本人が「この高校に行って良かった」と言っていたことです。通信制に関してとてもコンプレックスを持っていて、それを人に言えなかった彼が「良かった」と言えたところは、とても成長だなと思い、視野が広がったと感じました。さらに、通信制中等部にあるゲーム塾でゲームの講師のアルバイトをしているのですが、その中で「人に教える」ということに興味を持ちました。不登校や特性を持った子たちが、ゲームであればオンラインではなくオフラインでも校舎に集まってくる、ということがあり、eスポーツの教育的効果を感じ、人に教える仕事って面白いな、もっと学びたいと思っているようです。そこから、大学に行きたいというビジョンが見えました。
彼は、”eスポーツ”によって学校に行けなくなり、全てを失いました。しかし、”eスポーツ”によって将来のビジョンが見えてきている、という経緯がとても面白いなと思ってます。彼は大学に行くにはまだ学力が足りませんが、今回AO総合選抜型の入試に挑戦しました。惜しくも2次面接はだめでしたが、1次では自分の不登校についてを小論文で書いていました。不登校であっても、それが子どもたちの人生の足枷にならないような社会をつくるということをテーマにしていました。自分を振り返って、eスポーツをきっかけにオンラインでの居場所から始まり、オフラインでの居場所やそこでの役割を持つことができたこと、それを今後の教育プログラムに組み込めないか、というところまで提起していました。それは、この不登校の経験がなければ考えられなかったことだなと思います。
私自身も、当時から同じ環境の人たちと繋がれたことはとても大きな支えとなっています。今後私自身も、不登校の子の親だったからこそ、こんな面白い経験、体験ができたんだという風に言えるようになりたいなと思っています。
都立工芸高校の定時制に通っている高校1年生の女の子の母です。
娘は中学1年生の冬から学校に行けなくなり、それからずっと家に引きこもるようになって外に出られない状態でした。私自身も娘と同じように、半年くらいずっと外に出られませんでした。世田谷区で開催してくださっている「不登校保護者の集い」が家の近くで開催され、行ったことをきっかけに、似た境遇の保護者の方々と繋がることができました。私自身が居場所を見つけることができ、自分の話をしたり他の方の話を聞くことで不登校について知ることができました。それから月に1回保護者の集いに行くことで私自身不登校という現実と娘の苦しみに向き合うことができました。
こぐまの会(世田谷区で活動する不登校の子どもを持つ親の会)で子ども達の成長過程や進路など様々な情報やアドバイスをもらっていましたがいざ娘が中学3年生になり、進路がなかなか決まらず困っていました。本人は「まだ中2でいたい」と言いながら踏み出したくてもどうしたらいいのか分からず焦りや不安があったので先ほどご登壇なさった沖山校長にお願いして、3者面談をしていただきました。面談では、娘は1時間の内ほとんどしゃべらずに話をただずっと聞いていましたが、帰る時に「高校に行くなら学校らしい校舎があって広々としている方がいいな」と初めて自分が通いたい高校のイメージができました。
世田谷泉高校を受験すると決め、何度も親子で足を運びましたが、人混みが苦手な娘は渋谷での乗り換えで気分が悪くなり毎回苦労し不安に思っているようでした。出願後に、たまたま私が知人と話す中で「(娘には)工芸高校の定時制もいいんじゃないかな」と言われ、まだ志望校変更が可能な期間だったので工芸高校に個別見学をお願いしました。家から乗り換えなしで行けたことが嬉しかったのか、学校に着いてすぐ「ここなら一人で通えるかも」とホッとしている様子で、更に授業の様子を拝見しながら先生や生徒さんからの説明を受けて「ここに入りたい」と心が決まったようでした。ただ、一次募集の志望校を世田谷泉高校にした場合は工芸高校の定時制への変更は東京都の規定上できない決まりになっており、万が一世田谷泉高校を受験して受かった場合は二次募集で工芸高校を受験することができない為一次募集の日程では試験を受けませんでした。工芸高校の定時制が一次募集時に定員割れをしていれば二次募集で受験ができるので定員割れを祈りながら二次募集の案内が出るのを待ち、無事に受験し合格することができました。3月末近くに合格が出たのでぎりぎりまでハラハラドキドキしましたが、本人が行きたいと思える学校に出会え、最後まで諦めずに受験に臨めて本当に良かったです。私達家族だけでは乗り越えられなかった進学の壁も沢山の方々のお陰で乗り越えることができ、今は波はあるものの毎日学校に通っています。
娘は中学1年生の冬から学校に行けなくなり、それからずっと家に引きこもるようになって外に出られない状態でした。私自身も娘と同じように、半年くらいずっと外に出られませんでした。世田谷区で開催してくださっている「不登校保護者の集い」が家の近くで開催され、行ったことをきっかけに、似た境遇の保護者の方々と繋がることができました。私自身が居場所を見つけることができ、自分の話をしたり他の方の話を聞くことで不登校について知ることができました。それから月に1回保護者の集いに行くことで私自身不登校という現実と娘の苦しみに向き合うことができました。
こぐまの会(世田谷区で活動する不登校の子どもを持つ親の会)で子ども達の成長過程や進路など様々な情報やアドバイスをもらっていましたがいざ娘が中学3年生になり、進路がなかなか決まらず困っていました。本人は「まだ中2でいたい」と言いながら踏み出したくてもどうしたらいいのか分からず焦りや不安があったので先ほどご登壇なさった沖山校長にお願いして、3者面談をしていただきました。面談では、娘は1時間の内ほとんどしゃべらずに話をただずっと聞いていましたが、帰る時に「高校に行くなら学校らしい校舎があって広々としている方がいいな」と初めて自分が通いたい高校のイメージができました。
世田谷泉高校を受験すると決め、何度も親子で足を運びましたが、人混みが苦手な娘は渋谷での乗り換えで気分が悪くなり毎回苦労し不安に思っているようでした。出願後に、たまたま私が知人と話す中で「(娘には)工芸高校の定時制もいいんじゃないかな」と言われ、まだ志望校変更が可能な期間だったので工芸高校に個別見学をお願いしました。家から乗り換えなしで行けたことが嬉しかったのか、学校に着いてすぐ「ここなら一人で通えるかも」とホッとしている様子で、更に授業の様子を拝見しながら先生や生徒さんからの説明を受けて「ここに入りたい」と心が決まったようでした。ただ、一次募集の志望校を世田谷泉高校にした場合は工芸高校の定時制への変更は東京都の規定上できない決まりになっており、万が一世田谷泉高校を受験して受かった場合は二次募集で工芸高校を受験することができない為一次募集の日程では試験を受けませんでした。工芸高校の定時制が一次募集時に定員割れをしていれば二次募集で受験ができるので定員割れを祈りながら二次募集の案内が出るのを待ち、無事に受験し合格することができました。3月末近くに合格が出たのでぎりぎりまでハラハラドキドキしましたが、本人が行きたいと思える学校に出会え、最後まで諦めずに受験に臨めて本当に良かったです。私達家族だけでは乗り越えられなかった進学の壁も沢山の方々のお陰で乗り越えることができ、今は波はあるものの毎日学校に通っています。
私は仕事で臨床心理士をしていて、普段は児童精神科やスクールカウンセラーの仕事をしています。今日は心理士としてではなくて、あくまでも不登校を経験した子どもをもつ母親の一人として、皆さんに少しでも何かお伝えできればなと思います。
息子が不登校になったのは中学3年生の2月くらいだったと思います。はじめは頭が痛いとかお腹が痛いとか身体症状を訴えていたんですけど、そのうち学校に行かなくなりました。私なりに理解したのは、「今の彼にとって学校という居場所が安全じゃないんだな」ということと、「彼の心の中にはすごい雨が降っていて、雨の日が続いているんだな」ということでした。
とはいえ、頭ではそうだと分かってはいるものの、やはり私も感情がなかなか追いついていかず、何度も心が折れそうになりました。そのときに、こぐまの会のようなピアグループなど色んな心強いメンバーに支えていただいて、私も心理的な危機を乗り越えてこられたかなと思っています。
息子の不登校経験が私にとってどんな意味をもたらしてくれたのか、というものを考えたのですが、意外とシンプルで些細なことでした。それは、「彼が自宅で笑顔で笑ってくれること」とか、「どうでもいい私のおばさんギャグにツッコミながら一緒に食卓を囲めること」とか、「私が作ったお弁当を学校に持って行って食べてもらえること」とか。そういった本当に些細なことが自分にとってどれくらいありがたくて、愛おしくて尊いものなのかってことに気付かされました。「この子の将来や行く先はどうなるんだろう」みたいな親側の不安から、親が先回りして不安を解消しよう!とか、なんとか彼にアプローチしよう!とかしてみたくなるのですが、それをしても答えは出ないんだな、ということを感じました。無理をしても袋小路のままなので、時間をかけてゆっくりと子どもの成長や発達みたいなものを眺めてあげられたらいいな、ということを思いました。
こちらにいる方々はおそらく不登校について何らかのご関心がある方が多いと思います。本当に日々お子さんへの子育てに向き合い本当にお疲れ様です。本当にすごいことだと思います。お子さんの心の中で雨が降っている日は、親御さんの心も雨、もしくはあられ、いやもしくは雪がこんこんと降っている、ということも多いと思います。どうぞ世田谷区内の学校にいるスクールカウンセラーや教育相談など、行政のリソースも積極的に利用されて、ご自身の心のケアもして労われてください。
最後になりましたが、この場を与えてくださり、皆様ありがとうございました。
息子が不登校になったのは中学3年生の2月くらいだったと思います。はじめは頭が痛いとかお腹が痛いとか身体症状を訴えていたんですけど、そのうち学校に行かなくなりました。私なりに理解したのは、「今の彼にとって学校という居場所が安全じゃないんだな」ということと、「彼の心の中にはすごい雨が降っていて、雨の日が続いているんだな」ということでした。
とはいえ、頭ではそうだと分かってはいるものの、やはり私も感情がなかなか追いついていかず、何度も心が折れそうになりました。そのときに、こぐまの会のようなピアグループなど色んな心強いメンバーに支えていただいて、私も心理的な危機を乗り越えてこられたかなと思っています。
息子の不登校経験が私にとってどんな意味をもたらしてくれたのか、というものを考えたのですが、意外とシンプルで些細なことでした。それは、「彼が自宅で笑顔で笑ってくれること」とか、「どうでもいい私のおばさんギャグにツッコミながら一緒に食卓を囲めること」とか、「私が作ったお弁当を学校に持って行って食べてもらえること」とか。そういった本当に些細なことが自分にとってどれくらいありがたくて、愛おしくて尊いものなのかってことに気付かされました。「この子の将来や行く先はどうなるんだろう」みたいな親側の不安から、親が先回りして不安を解消しよう!とか、なんとか彼にアプローチしよう!とかしてみたくなるのですが、それをしても答えは出ないんだな、ということを感じました。無理をしても袋小路のままなので、時間をかけてゆっくりと子どもの成長や発達みたいなものを眺めてあげられたらいいな、ということを思いました。
こちらにいる方々はおそらく不登校について何らかのご関心がある方が多いと思います。本当に日々お子さんへの子育てに向き合い本当にお疲れ様です。本当にすごいことだと思います。お子さんの心の中で雨が降っている日は、親御さんの心も雨、もしくはあられ、いやもしくは雪がこんこんと降っている、ということも多いと思います。どうぞ世田谷区内の学校にいるスクールカウンセラーや教育相談など、行政のリソースも積極的に利用されて、ご自身の心のケアもして労われてください。
最後になりましたが、この場を与えてくださり、皆様ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。
それぞれの保護者の方が、お子さんと向き合い、ともに時間を過ごす中で感じた悩みやしんどさ、喜び、嬉しさなど様々な想いが溢れる内容でした。多くの方が本会を主催したこぐまの会のような保護者の会でのつながりや支援機関などとつながりによって支えられたというお話をされていました。
本サイトでは世田谷区内の様々な保護者の会や子どもの居場所などの支援情報を掲載しています。また、様々なイベント情報も掲載しています。ぜひご覧ください。